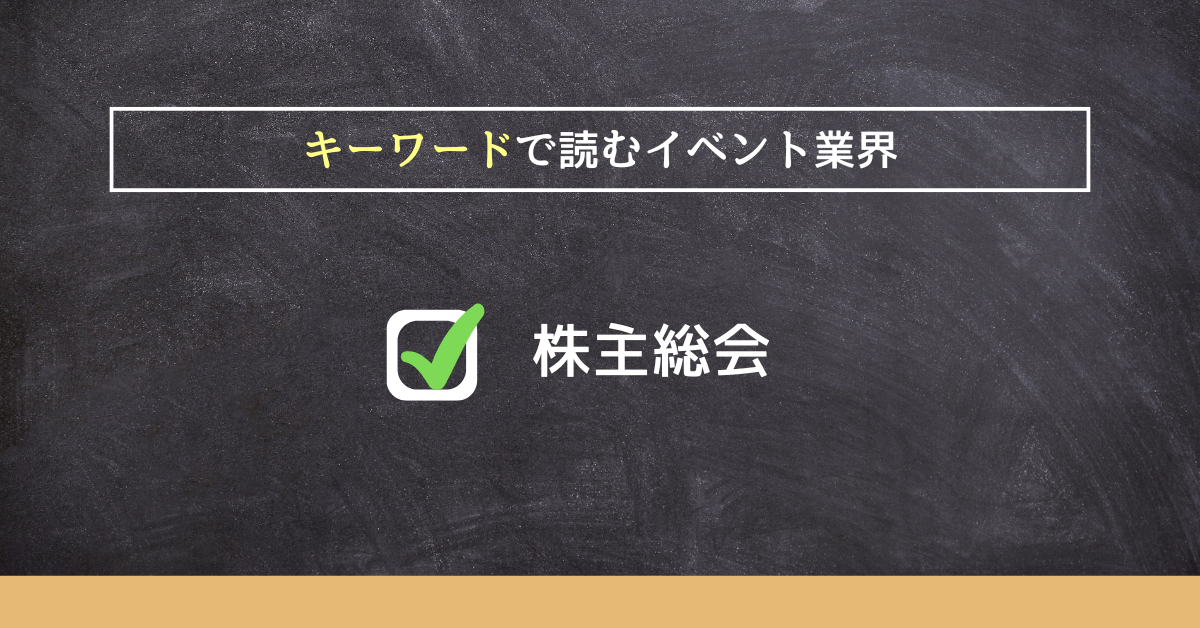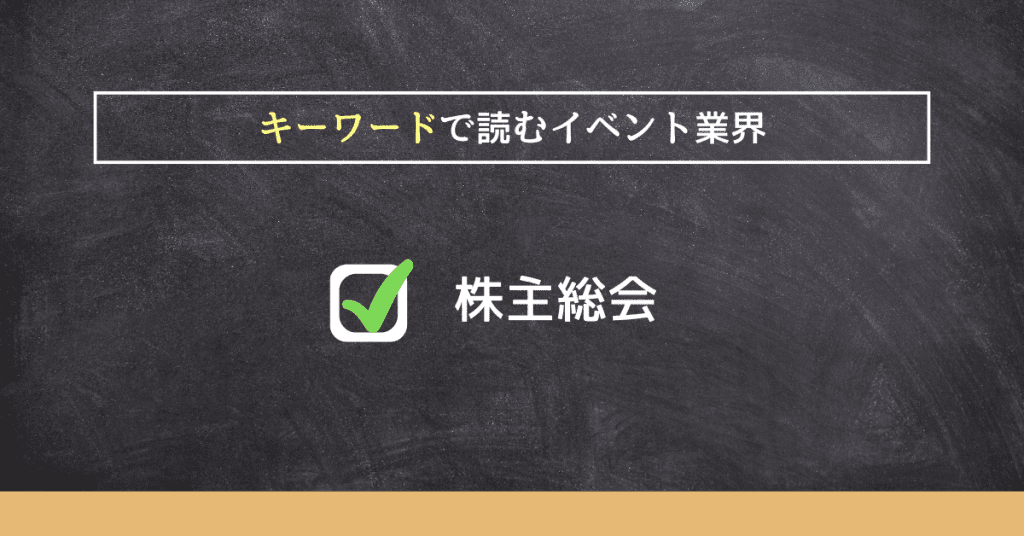
近年はオンラインやハイブリッド形式の開催が一般化しつつある。単なる配信ではなく“演出の場”としても位置付けられており、照明・音響・映像構成・カメラワーク・リスク対策など、イベント的要素が求められるケースも多い。
キーワードをさらに詳しく!
[インタビュー]株主総会は“伝える”イベントへ。映像演出が企業ブランドを支える
近年、株主総会を「議案を通す場」から企業の姿勢やブランドを発信する対外イベントとして捉える動きが広がっている。情報開示やステークホルダー向け広報を支援するプロネクサスと映像演出に強みを持つシネ・フォーカスは、グループ会社として連携し、株主総会の表現力を高める取り組みを重ねてきた。両社に籍を置き、現場と企画の双方に関わる小山氏に、株主総会の変化と“企業イベント”としての可能性を聞いた。
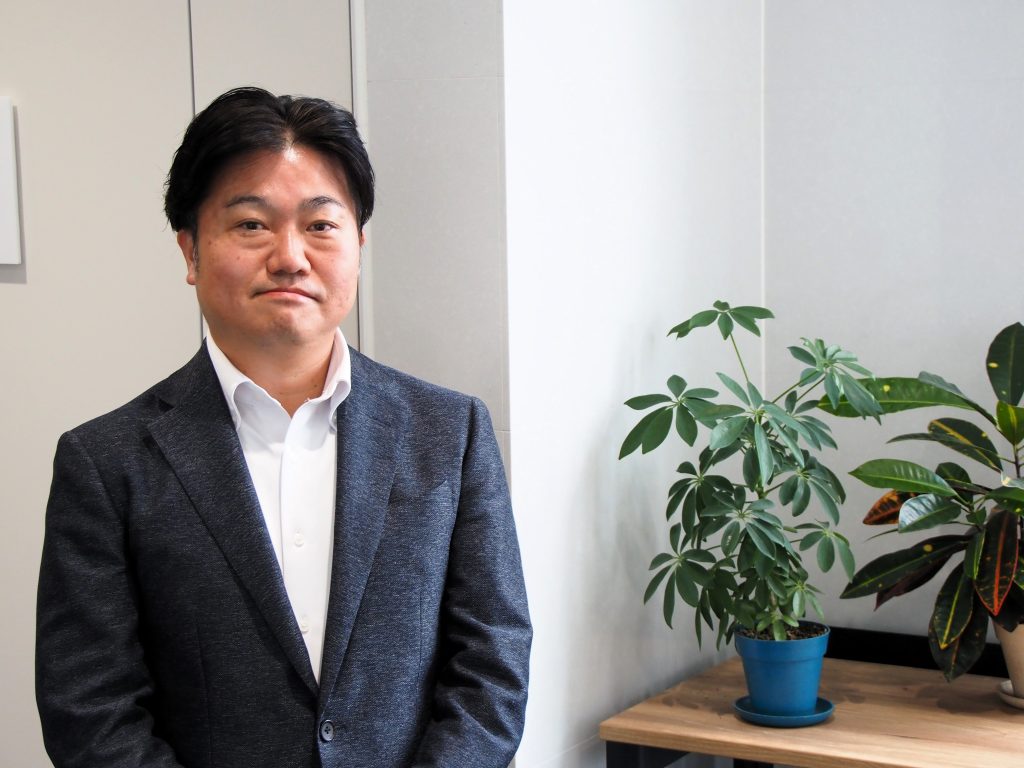
株式会社シネ・フォーカス 営業開発室 主任
小山 貴士 氏
演出と対話が企業の姿勢を映す
――近年、株主総会にどのような変化が見られますか
小山 かつての株主総会は、議案を通すための形式的な場と見なされることもありましたが、現在では「年に一度、株主と対話できる貴重な機会」として位置付けられるようになっています。特に個人株主の増加や機関投資家からの株主提案の活発化により、企業は伝える力がより一層求められています。その中で、映像やグラフィックを活用した視覚的なプレゼンテーションが重要な役割を果たしています。
例えば、PowerPointで作成した事業報告資料に、ユニバーサルフォントや見やすい色彩設計を取り入れることで、全ての株主に伝わりやすい表現にしています。さらには、ナレーションやアニメーションを組み込んだ動画を活用し、情報をより効果的に伝える手法も広がっています。
また、ライブ配信やオンデマンド配信の導入により、来場できない株主ともコミュニケーションが可能になりました。最近では、リアル開催とオンライン配信を併用するハイブリッド型が主流です。
――演出面については
小山 以前に比べて、情報をいかに分かりやすく、印象的に伝えるかという視点が強くなっています。中でも社長自らが将来ビジョンを語る場面では、映像演出と組み合わせることで株主との距離感がぐっと縮まります。
――まさに企業の顔としてのプレゼンテーションですね
小山 最近は議長席から一歩出て、ステージ前に立って語りかけるような場面もあります。シナリオをただ読むのではなく、自分の言葉で熱を込めて話すことで、企業への信頼感やファン化にもつながっていきます。
とある株主総会では、若い個人株主から「この会社が求める人物像とは?」という質問が出ました。それに対し、議長である会長が企業理念とこれからの人材像を自らの言葉で熱く語り、会場から拍手が起きたのが印象的でした。
開かれた株主総会に向けた工夫
――ユニバーサル対応に関して、どのような取り組みがありますか
小山 聴覚障害のある株主に向けて、字幕表示や手話通訳などの提案などを進めています。今年、当社ではオンラインでの手話通訳やAI字幕を活用した株主総会も実施しました。また、多様な方々と向き合ううえで必要な「マインド」と「アクション」を体系的に学べる株主総会版の「ユニバーサルマナー検定」も行っています。
「ハード(機材)は変えられなくとも、ハート(心配り)は今から変えられる」という言葉を胸に、全ての株主が安心して参加できるような空間づくりを心がけています。
――ライブ配信やハイブリッド開催については、どう評価されていますか
小山 コロナ禍で一気に普及したライブ配信ですが、現在も一定の需要があります。リアルで参加できない方に向けて、ライブ配信やオンデマンド配信の選択肢があることで、総会の開かれ方が広がりました。一方で、リアル会場の演出が主軸であることは変わらないとも思っています。配信はあくまで補完的な手段であり、リアル会場の安定運営があってこそ成立するという考えです。
――総会では、万が一に備えたリスク対応も重要かと思います。どのような準備をされていますか
小山 イベントにトラブルはつきもの、という前提で準備をしています。機材が故障したときのために予備のケーブルやモニターを用意したり、配信機材も冗長化(バックアップ体制の整備)しています。配信が落ちても対応できる体制を整えているのです。
さらに、ソフト面でも株主からの突発的な質問や混乱に備えて、想定ケースをもとにリハーサルを行います。これは株主総会に限らず、企業イベント全体に通じる備えです。
――クライアント側のニーズに変化はありますか
小山 コロナ禍ではライブ配信に関するご相談が非常に多かったのですが、現在はリアル会場の質を上げたいという声が増えています。「もっと分かりやすく」「映像演出を強化したい」「スタッフ体制を充実させたい」など、株主総会を見せる場としてブラッシュアップしたいという傾向があります。
これからは、企業と株主の心理的距離をより縮める方向に進んでいくと感じています。ただし、リスクマネジメントやセキュリティ面への配慮も欠かせません。そのバランスを保ちながら、安全性と開かれた運営を両立させることが私たちの使命だと考えています。
.png)